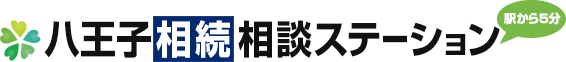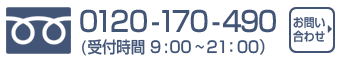生前における相続税対策
相続税は、相続人が亡くなった時点の相続財産について課税するようになっています。しかも、その金額が大きければ大きいほど、税金も高くなる仕組みです。
そこで、相続税を減らすためには、相続財産自体を減らすことが考えられます。ただし、単純にお金を使ってしまうのでは意味がありません。

生前における相続税対策としては、主に以下の5つが考えられます。
1.毎年生前贈与することで、相続財産そのものを減らす。
2.死亡保険金の非課税枠を利用する。
3.死亡退職金の非課税枠を利用する。
4.養子縁組をして相続人を増やし、税金を下げる。
5.賃貸マンションを新築し、現預金と土地の評価を下げる。
どれも相続税対策には有効なので、相続が起こる前に専門家に相談したうえで、計画的に実行することをお勧めします。
1. 毎年、生前贈与することで、相続財産そのものを減らす

相続税は、相続開始の時点で所有している財産に課税されるようになっています。
なので、生前において毎年、少しずつ贈与をすることで相続財産そのものを減らし、相続が起きたときの相続税を減らすという方法です。
暦年贈与であれば、贈与をしても年間110万円までは、非課税となります。
これは、贈与者1人に対しての計算になりますので、受贈者が3人いらした場合は、それぞれ110万円まで、合計330万円まで非課税とすることができます。
これを10年間行うことで、合計3300万円ほど相続財産を減らすことができます。
現在の相続税率は10~50%なので、節税効果は少ない人で330万円、多い人だと1650万円にもなります。
ただし、贈与かどうかの判定は、税務署との意見が分かれるところなので、しっかりと贈与の事実を残した方がいいでしょう。
具体的には
1.贈与者と受贈者の間で契約書を交わす
2.贈与者の口座から受贈者の口座に直接振込む
3.贈与税の申告をしておく
などの、対策をとっておけば万全でしょう。
何も資料を残さないで、贈与と主張しても認められることはまずありません。事前の対策が重要になります。
2. 死亡保険金の非課税枠を利用する
現在所有している現預金を、生命保険にすることで、法定相続人1人当たり500万円が非課税となります。
相続人が、配偶者と子2人の合計3人であれば、1500万円までが非課税の金額となります。
現在の相続税率は10~50%なので、節税効果は少ない人で150万円、多い人だと750万円にもなります。

この節税には『一時払終身保険』を利用したケースが多いです。
・契約者被相続人
・被保険者被相続人
・受取人相続人
として、契約し、被相続人の預金口座から保険料の一時払いを行います。
こうすることで、被相続人の預金口座は減少する代わりに、相続が起こった場合には、相続人は非課税で受け取ることができます。
※間違った手続きで、加入しないためにも、生命保険に加入する際には、必ず専門家に相談してから生命保険の加入をしてください。
当事務所は、生保代理店も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
3. 死亡退職金の非課税枠を利用する

死亡退職金を相続でもらう場合、2の死亡保険金と同様の非課税枠が別枠で使うことができます。
したがって、2の死亡保険金と合わせると2倍の効果を得ることができます。
しかしこれを狙って使うには、自分の会社をお持ちでないと使えませんが、自分の会社をお持ちであれば非常に有効な手段になり得ます。
死亡保険金として、支給を受けるためには、会社で財源を用意する必要があります。そのため、会社で生命保険に加入したり、小規模企業共済に加入するなどの退職金を支給できる環境を整備する必要があります。
4. 養子縁組をして相続人を増やし、税金を下げる
相続税は、同じ相続財産であっても、法定相続人が多ければ多いほど相続税が安くなるようになっています。
これを利用して、養子縁組を行い相続税を下げる方法です。

例えば
相続税が課税される財産が3億円の場合の相続税は
法定相続人が2人の場合(子供2人の場合)5800万円
法定相続人が3人の場合(子供3人の場合)4800万円(孫養子)
となり、同じ相続財産であっても相続人の数の増加により、相続税が1000万円も軽減されます。
よくあるケースとしては、一家を引き継ぐ予定である長男のお孫さんを養子にすることです。
長男のお嫁様を養子にすることもありますが、仮に離婚をした場合に養子の解除もする必要があり、トラブルにつながりかねず、あまりお勧めできません。
なお、相続税の計算を行う上では、養子は1人まで法定相続人に加えられます。(民法では養子は何人でもOKです)
また、副次的になりますが、相続人が1人増えると、1人分の非課税枠が増えるメリットがあります。
死亡保険金の非課税枠500万円
死亡退職金の非課税枠500万円
生命保険や退職金を絡めると、合計で1000万円も非課税枠が増えるため、さらに節税効果大きくなります。
5. 賃貸マンションを新築し、現預金と土地の評価を下げる

相続が起きたときの建物の相続税評価額は、実際にかかった建築費用ではなく、固定資産税評価額で評価します。
この固定資産税評価額は、建築費の50%以下になることも多く、その特性を利用して、節税を図ることができます。
例えば
現金で1億円持っているよりも、その現金を使って1億円の建物を建てることで、相続税評価額を5000万円下げることができます。
現在の相続税率は10~50%なので、節税効果は少ない人で500万円、多い人だと2500万円にもなります。
さらに、この建物が賃貸住宅であれば、借家権割合を30%引くことができますので、さらに節税効果が高まります。
稀に、借金をしてアパートを建てると相続税を減らすことができると、説明する人がいますが、これは必ずしも正解ではありません。
単純に借金をするのではなく、その借金を建物に変えることで節税が図れますので、現金のある方は必ずしも借金をする必要はありません。
ただし、注意して頂きたいことがあります。
相続税は期限内の現金一括納付が原則です。
したがって、現金をすべて不動産にしてしまうと、相続税の対策は図れますが、相続税の納税資金に困ることになります。
上記1~4の節税手法も上手に利用することで、相続税の納税資金を確保しつつ、納税資金が厳しいようであれば、建築の際に借入することも検討されてみてはいかがでしょうか。